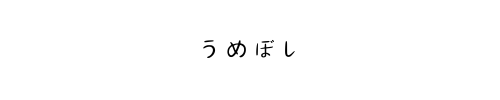法人は個人事業主の場合と異なり、「法人、株主」というものが存在します。個人事業主においてはこれらの者は登場しません。
そして法人には「法人、株主」が登場するため、「株主法人間取引」が発生し、さらに「株主法人間取引に係る課税関係」が発生します。
この「株主法人間取引に係る課税関係」に関する特別のルールを定めているのが法人税法です。そして、そもそも「法人、株主」という者が登場しない所得税法の世界では当然に当該課税ルールは存在しません。
今回は「株主法人間取引に係る課税関係」のうち法人から株主になされる「配当に係る課税関係」を詳しく見ます。
法人が事業活動を行って利益を得た場合、その利益に対して法人税が課税され、課税済みの利益が株主に配当されます。そして配当を受けた株主は配当所得を得ているので、これに対して所得税が課税されます。この法人と株主に対する課税について、以下の2つの見方があります。
①「法人税は株主が受ける配当所得に対する所得税の前取りである」という見方
②「法人税は株主が受ける配当所得に対する所得税の前取りではなく、法人に課された税金である」という見方
これら①、②の見方を説明するとともに現行の法人税法はどのように規定しているのか、その他もろもろの関連事項について解説します。
なお「法人税と所得税の統合」というものが記事の中で登場しますが、これは「法人が利益を獲得すると、この利益に法人税が課税されるが、これは株主が配当所得を得たときに課される所得税の前取りとみなし、当該課税済みの利益が株主に配当された時に株主の配当所得に課税するのは二重課税となるので、この二重課税を排除するための仕組み」という意味です。
①「法人税は株主が受ける配当所得に対する所得税の前取りである」という見方
✔概要
幾人かの出資者が出資を行って一つの事業体を作り、その事業体が獲得した利益を出資した者に分配する。
この場合、利益の分配を受けた出資者(株主)は「配当所得」を得ているので、当然に所得税が課されます。
事業体(法人)が利益を獲得したときに、当該利益に法人税を課するということは、株主の配当所得に対する所得課税を法人の段階で課税していると考えられるので、「法人税は配当所得に対する所得課税の前取り」であると説明できます。
この考え方によると「法人税は株主がすべて負担している」ということになります。
そうであるなら、法人段階で法人利益に課税することで株主の所得税を前取りし、株主に課税済みの利益を配当したときに、当該利益に所得税を課税するなら、同じ利益に二重課税されていることになるので、法人税と所得税を統合して二重課税を排除すべきということになります。
✔反対意見
法人には「消費者、仕入先、金融機関、株主、従業員など」様々な利害関係者が存在します。それでは、この法人税を誰に負担させるのかというと、それは「逃げ道のない立場の弱い者」が負担を強いられると考えられます。
消費者、借入先、株主は「逃げ道のある者」です。これらの者に税負担を転嫁すればどうなるでしょうか。価格が上がれば消費者は自社製品ではなく他社製品を買えますし、利息の減額を要求すれば金融機関は当社以外に融資先を探します。配当が減れば株主は当社の株を売ることもできます。このように「逃げ道のある者」に税負担を転嫁すると逃げられてしまうため、転嫁が難しいのです。
一方、立場の弱い仕入先や従業員は「逃げ道のない者」です。立場の弱い仕入先は契約を切られれば仕事を失い、従業員も生活のため簡単には会社を辞められません。結果として、仕入価格の引き下げや賃金の抑制という形で、税負担がここに集中します。
このように考えると法人税を負担しているのは主に「逃げ道のない者(仕入先や従業員)」であり、逃げ道のある株主は法人税の一部しか負担していないと考えられます。
よって「法人税は100%株主の配当所得の前取りであるという考え方は適切ではない」というのが反対意見の主張です。
②「法人税は株主が受ける配当所得に対する所得税の前取りではなく、法人に課された税金である(即ち法人が法人税を負担している」という見方
✔概要
法人税は株主の配当所得に対する所得税の前取りではなく、法人に対して課された税金である(即ち法人が法人税を負担している)とする見方です。
法人は国から「有限責任性、株式流動性、エージェンシー・コストの減少」という利益を受けているのでその対価として法人税を支払っていると考えるのです(法人税を課税する理由参照)。
法人が国から受けている利益である「有限責任性、株式流動性、エージェンシー・コストの減少」について以下に簡単に説明します。
有限責任性・・・「法人が倒産しても、株主は出資額以上の損失を被ることはない、という株主有限責任を国が制度として認めている」ので、これを法人が国から受けている利益と考えるのです。
株式流動性・・・「株主は株式を購入しても、それを安定した証券市場で売却することで投資リスクを軽減でき、そのような証券市場を政府が維持・管理している」ので、これを法人が国から受けている利益と考えるのです。
エージェンシー・コストの減少・・・「もし仮に法人税が存在せず、会社から配当を受けた株主に直接課税する仕組みだとすれば、法人の利益獲得活動に対する個々の株主の立場が異なるため、株主間で意見が対立してしまいます。(例えば所得の多い株主Aさんはこれ以上配当を貰うと、高い税率が適用されるのであまり配当してほしくないと考えるし、逆に所得の少ないB株主さんはもっと多くの配当をしてもらいたいと考えるため、AさんとBさんで意見が対立する)。法人税はそのような株主同士の意見対立を緩和する」ので、これを法人が国から受けている利益と考えるのです。
✔反対意見
ある人が稼いで所得(端的に言うとお金)を得た場合、その所得を消費に回すことで心理的満足を得ることができます。
たとえばお金を使ってハンバーガーを購入し、食べることで「おいしい」という心理的満足を得ることができますし、お金を使って映画のチケットを購入し、映画鑑賞することで「面白かった」という心理的満足を得ることができます。
「所得(お金)=心理的満足」と考えるのが包括的所得概念です。使ったお金はそれでもって心理的満足を受けていますし、使っていないお金(貯蓄)は将来、消費に回すことで心理的満足を得ることができます。
しかし消費によって心理的満足を受けることができるのは「生身の人間」であり、「法人」は消費することはできず、よって心理的満足を得ることもできません。
つまり、法人には消費による「心理的満足」が帰属しない以上、「所得=心理的満足」であるため、法人に所得が帰属することもあり得ません。
法人に所得が帰属しない以上、所得に課される租税を法人が負担することもあり得ないのです。よって「法人税は法人に課される税金ではない」ため、当該説には無理があるという理屈です。
現行法の取扱い
✔現行法は部分的な二重課税の排除(法人税と所得税の不完全統合)を行っている
現行法は「法人が利益を得たときは法人税を課税し、株主が配当を受けたときは当該配当に所得税を課税するとともに、配当控除(所得税法92条)という税額控除を認めています」。
そして「配当控除」は完全な二重課税の排除ではなく、部分的な二重課税の排除を行う仕組みになっています。
法人税と所得税の統合(完全な二重課税の排除と部分的な二重課税の排除)
法人税を株主の配当所得に対する所得税の前取りであると考えると「完全な二重課税の排除」が必要となります。
たとえば法人の利益が1000、法人税率20%、法人から配当を受ける株主の所得税率が40%であったとします。この場合は法人税と所得税トータルで「1000×所得税率40%=400」課税すべきです。
そして法人段階において「1000×20%=200」課税しており、株主段階で「800×40%=320」課税しているため「200+320ー400=120」の配当控除(税額控除)をすれば、法人税と所得税トータルで「1000×所得税率40%=400」課税となり、完全な二重課税の排除(法人税と所得税の完全統合)となります。
しかし、現行法は部分的な二重課税の排除(法人税と所得税の不完全統合)をしています。たとえば上記の例において配当控除を120ではなく、50しか認めないような規定になっています。
✔現行法が部分的な二重課税の排除(法人税と所得税の不完全統合)を行う理由
このように現行法が部分的な二重課税の排除(法人税と所得税の不完全統合)を行う理由は定かではありませんが、考えられる理由として次のようなものがあります。
・法人税は株主のみが負担するのではなく、法人の様々な利害関係者が負担しており、株主はその一部のみを負担していると考えられるため、部分的な二重課税の排除をしている。
・単に、配当所得について配当控除を認めることで、配当への課税を軽課し、株式市場に良い影響を与えようとしている。
現行の配当控除制度
株主が配当金を受け取ったとき、現行の所得税法においては「受取配当の10%または5%の配当控除(税額控除)」が認められています。
10%または5%のいずれの配当控除が認められるかは「課税総所得金額」を基準に判断します。
① 配当所得を含めた課税総所得金額が1000万円以下の場合
受取配当の額の10%が配当控除(税額控除)される
② 配当所得を含めない課税総所得金額が1000万円超の場合
受取配当の額の5%が配当控除(税額控除)される
③ 受取配当の額を含めない課税総所得金額は1000万円以下であるが、受取配当の額を含めた課税総所得金額が1000万円を超える場合
・受取配当の額を含めない課税総所得金額(例えば700万円)に受取配当の額(例えば500万円)を加算していって、その合計額が1000万円以内の受取配当の部分(1000万円-700万円=300万円)→受取配当の額の10%が配当控除(税額控除)される
・受取配当の額を含めない課税総所得金額(例えば700万円)に受取配当の額(例えば500万円)を加算していって、その合計額が1000万円を超える受取配当の部分(700万円+500万円ー1000万円=200万円)→受取配当の額の5%が配当控除(税額控除)される
このように現行の配当控除制度は「株主の受取配当の額と課税総所得金額」さえ分かれば、配当控除の額を計算できるようになっています。
つまり現行制度上、配当控除の額は「法人税と所得税の統合」という観点から計算している訳ではないので、必然的に「不完全な二重課税の防止(法人税と所得税の不完全な統合)」となるのです。
現行法以外の統合の方法
現行法において採用されていませんが、配当に係る法人税と所得税の統合方法には、以下のような方式もあります。
✔組合方式
これは、法人が利益を獲得した段階で、その利益を株主の持分に応じて配賦し、株主に配賦された金額に応じて所得税を課する方法です。この方法では実際に株主に配当がなくても配当所得に対する所得税が課税されることになります。
そしてこの方法は法人税を課さず、株主が配当を受けたと仮定しての所得税を課するため、完全統合の一種となります。
この方式は「課税の繰延を防ぐことができる」という利点があります。
つまり、現行法の課税方法は「法人利益に課税した後、課税済みの利益を株主に配当をしたときに当該株主の配当所得に課税する」という「二段階課税方式」を採用しています。この場合株主への配当を行わず、利益を法人内部に留保した場合、「株主に対する配当所得課税」は行われずに、当該課税が繰り延べられてしまうという問題があります。しかし組合方式は法人に課税を行わず、個人株主だけに課税を行うという「一段階課税方式」であるので、所得に対する課税が繰り延べられるという問題を解消できるのです。
しかし、この方法にはいくつかの欠点があります。
ひとつは、株主は実際に配当を受けていないのに配当所得として所得税が課税されるので、納税資金がないという問題があります。
また、この方式を多数の株主が存在する大企業に採用した場合、当該株主に課される所得税は、企業が源泉徴収する方法が取られると思われます(配当を受けていない株主などが申告しないことが考えられるため)。この場合、企業は個々の株主の所得税率を把握する必要があり、執行コストが莫大となり現実的に採用することは困難です。
✔インピュテーション方式
この方式は、法人が利益を得たときはまずこの利益に法人税を課税し、その後、株主に配当するときに当該法人税を配当の額に加算した上で、その合計額に所得税を課税し、当該所得税額から加算した法人税額を控除して所得税の納税額を算出するというものです。
例えば、法人利益が1000、法人税率20%、株主が配当を受けた時に適用される所得税率が30%であるとします。
まずは、法人利益1000に対して法人税が200課税されます(法人利益1000×法人税率20%=200)。そして残額の利益800を株主に配当するときに、配当800に法人税200を加算した1000に対して所得税(30%)を課税し、算出された所得税額300から法人税額200を控除することで所得税の納税額100を計算します。
完全統合に基づくと、納付されるべき税金は1000×所得税率30%=300ですが、この方式によると「法人税額200+所得税額100=300」が納税されることになるため、完全統合の一種と言えます。
しかし、この方式は「法人段階課税と株主段階課税」という二段階課税方式を採用しているため、利益が法人内部に留保され配当がなされない部分は「株主段階課税」は行われておらず、この部分につき課税の繰延が行われることになります。
現行の二段階課税(法人課税+配当課税)において考えられる節税手法
個人事業主の場合は、事業で稼いだ所得に対して所得税が課税されます。他方、法人の場合は事業で稼いだ所得に対してまず法人税が課税され、その後配当により所得課税がなされます。つまり個人は一段階課税ですが、法人の場合は二段階課税がなされるのです。
この違いを利用した節税手法をいくつか紹介します。
✔法人成り
たとえば、個人事業主のままだと、事業所得に所得税の最高税率45%が適用されるとします。
そしてこの個人事業主が法人成りをすると、当該所得に対して法人税率23,2%が適用されるとします(法人成りした当該個人事業主は、当該法人の役員兼株主になるとします)。
そうであるなら法人成りをして事業所得に対して税率23,2%が適用された方がお得です。しかし法人の場合は二段階課税であるので、法人の利益を株主である自分(経営者)に配当してしまうと、当該配当に所得税が課税されてしまいます。
そこで配当を行わずに利益を法人内部に留保してしまえば、税率23,2%の適用だけで済むのです。もっとも留保金課税制度(法人税法67条)というものがあり、配当を行わずに利益を留保し続けると、その留保利益に法人税が課税されますが、留保金課税の対象となるのは資本金の額が1億円超の法人のみであり、日本の法人のほとんどは資本金1億円以下なので、小規模な法人はこの規定の適用を受けることはありません。
✔法人成りと相続
個人事業主である経営者が死亡し、その親族が事業を相続する場合、事業上の財産を相続することになるので、相続税が発生します。
他方、法人成りをした経営者兼株主が死亡し、その親族が事業を相続する場合、その法人の株式という資産を相続するため、相続税が発生しますが、法人財産そのものを相続するよりも財産評価額が低く算定される傾向にあるため、法人成りをして株式を相続するという形を取った方が税金上お得と言えます。
さらに法人が稼いだ利益を配当しないで、法人内部に留保し、経営者が死亡することで相続を行った場合、配当をしなかった部分が株式という形で相続されるため、税金上お得になります(もしも経営者が生前に配当を受け取っていたなら、経営者の手元に配当分のお金があり、お金を相続するという形になってしまうため、相続税上不利となる)。
✔配当利益をキャピタルゲインに転換する
たとえば、上場株式から配当を受ける場合、所得税率45%が適用されるとします。他方、上場株式を譲渡した場合、15%の所得税率が適用されます(租税特別措置法37条の11第1項)。
そうであるなら、法人が配当をせずに株主が株式譲渡を行なえば(すなわち、配当利益をキャピタルゲインに転換すれば)、45%の所得税率の適用を回避して15%の適用で済むことになります。
法人が配当を行う理由
法人の配当について、現行法は二段階課税を行っています。すなわち、法人の利益にまず課税し、株主に配当することで配当課税を行います。
このように法人の配当について「法人課税+配当課税」という二段階課税を採用しているなら、配当を行わずに企業内部に利益を留保した方が、配当課税による資金の流出がない分、お得です(株主は配当を受けることができないが、その分保有する株式の価値は高まるため、損はしない)。
このように配当を行うことにより配当課税を受け、その分税金上損をしてしまうのに、配当を行う理由は以下のように説明されます。
法人は税制上不利であるにもかかわらず配当をするのは、自らがそれだけ高い収益性を持つ将来性有望な企業であると投資家にアピールすることができ、そのことが株価の上昇につながり、将来高い株価による資金調達が可能となると考えるからです。
しかし、このような行動はマネー・バーニング(自分が金持ちであることを示すために無意味にお金を燃やす行為)に繋がるという批判もあります。