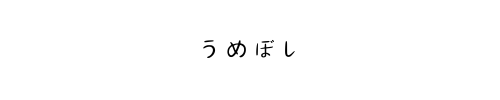法人税は法人の所得に対して課税されます。よって「法人税の負担者は法人である」ことになりますが、法人は生身の人間ではないため、法人税を負担することができないと理論的に考えられています。
それでは「法人に課された法人税の負担者は誰なのか?」について順を追って解説します。
なぜ法人の所得に課税するのか
国が法人に対して課税するときに、その対象がなぜ「所得」であるのか?
つまり、法人の「所得」以外のもの、たとえば外形標準課税のように会社の資本金の大きさなどを課税の対象とせずに、なぜ「所得」を課税対象にしたのか?という疑問です。
この疑問に対する主な理由は以下のとおりです。
個人で事業を行った場合、その「儲け」に所得税が課税されます。そしてもしもこの個人事業を法人事業として行っても、やっていることは同じです。よって法人が事業を行った結果「儲け」が出たなら、当然にその「儲け」に法人税が課されるということです。
また、法人も個人事業主と同じく国から公共サービスの提供を受けているので、その対価として法人税を支払うべき、とも説明されます。
法人は租税を負担することができない
個人が所得を得た場合、その所得を消費に回すことで「心理的満足」を得ることができます。
つまり、その所得を使って食べ物を買って食べることで満足したり、また所得を使ってチケットを購入し映画を見て満足することもできます。
そして消費に回されていない所得も、それを将来的に消費に回せば、「心理的満足」を受けることができます。よって「個人が得る所得=心理的満足」とするのが包括的所得概念の考え方です。
しかし、法人は生身の人間ではないので消費することができず、法人が「心理的満足」を得ることはできません。
よって包括的所得概念の考え方からすれば、法人には心理的満足がないので所得が帰属することはないと説明されます。法人に所得が帰属しないのであれば、法人は所得に対する租税を負うこともできないことになります。
法人が実質的に法人税を負担できないと考えるなら、たとえ法律で法人に法人税を課したとしても、その負担を法人以外の誰かに押し付けることになります。
もしも法人税の負担分だけ、株主の配当が減少するのであるなら、法人税の負担は株主に転嫁されていると考えられます。
しかし、法人を取り巻く関係者にはたとえば「消費者や仕入先、従業員」などがいます。もしも法人税負担を消費者に転嫁するなら、販売価格を上げることになるし、仕入先に転嫁するなら、仕入価格の値引きを要求するし、従業員に転嫁するなら、賃金を下げることになります。
そうすると、法人税負担を誰に転嫁しているのかは会社毎によって異なることになり、転嫁先を決めつけることはできません。
そのような中で現行の法人税法は法人税の一部は株主に転嫁されていることを前提として法律を作成しています(法人税は株主が配当を受け取ったときに課される所得税の前取りであるとして法律構成していると考えられる)。