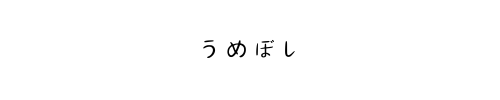今回は「貸倒損失」をメインに解説します。
「貸倒損失」は債権が貸し倒れて全額回収不能になった場合に計上されます。
企業会計上「貸倒損失」を計上した場合、法人税法においてどのような取扱いがなされているのか、また貸倒引当金との関係性や「貸倒損失」が論点となった興銀事件などにも触れて解説したいと思います。
貸倒損失の概要
「貸倒損失」は企業が保有する債権につき、その債権の全額が回収不能であることが確定したときに計上します。つまり、部分的に回収不能になった場合や債権の全額の回収不能が確定していない場合は「貸倒損失」は計上できません。
具体例を使って説明します。
当社はA社に対して100万円の売掛金を保有していましたが、A社が倒産したためにその全額の回収不能が確定しました。
この場合の仕訳は
貸倒損失 100万円/売掛金 100万円
となります。
そして、当該「貸倒損失100万円」は企業会計上「特別損失」として損益計算書に計上されます。
貸倒引当金の概要
これに対して「貸倒引当金」は企業が保有する債権につき、その債権の全部または一部が回収不能と見込まれる場合に計上します。
具体例を3つ使って説明します。
具体例1
当社はB社に対して100万円の売掛金を保有していましたが、過去3年間の貸倒れが2%であるため、当該100万円の売掛金に対して2%の貸倒引当金を設定しました。
この場合の仕訳は
貸倒引当金繰入額 2万円/貸倒引当金 2万円
となります。
この貸倒引当金繰入額2万円は、当社の本業の売上に関連して生じる費用なので、損益計算書上「販売費および一般管理費」として計上します。
具体例2
当社はC社に対して、本業以外の部分で100万円を貸し付けていました。そして当該貸付金に3%の貸倒引当金を設定しました。
この場合の仕訳は
貸倒引当金繰入額 3万円/貸倒引当金 3万円
となります。
この貸倒引当金繰入額3万円は、当社の本業外で生じる費用なので、損益計算書上「営業外費用」として計上されます。
具体例3
当社はD社に対して1000万円の売掛金を有していましたが、D社の業績が著しく悪化し、当該売掛金1000万円の回収に懸念が生じたので、50%の貸倒引当金を設定しました。
この場合の仕訳は
貸倒引当金繰入額 500万円/貸倒引当金 500万円
となります。
債権につき、臨時かつ巨額の貸倒が見込まれる場合には、当該債権を「貸倒懸念債権」として区分し、貸倒引当金を設定します。そしてその引当金繰入額は、損益計算書上「特別損失」として計上します。
以上、貸倒損失と貸倒引当金の企業会計上の取扱いをまとめると以下のようになります。
・債権の全額が回収不能であることが確定している場合・・・企業会計上「貸倒損失」を計上
・債権の全部または一部が回収不能と見込まれる場合・・・企業会計上「貸倒引当金繰入額」を計上
債権の全額の回収不能の確定による貸倒損失の法人税法上の取扱い
債権の全額につき回収不能が確定することにより、企業会計上「貸倒損失」を計上した場合には、当該損失は客観的に確定しているので、法人税法22条3項3号の「損失」として損金算入が認められます(法人税法22条3項3号(損失)の概要と法人税法33条との関係性参照)。
債権の全部または一部につき回収不能が見込まれることにより計上される貸倒引当金繰入額の法人税法上の取扱い
債権の全額またはその一部につき、貸倒れが懸念されることで企業会計上、貸倒引当金を設定した場合、上記のように損益計算書上、販管費、営業外費用、そして特別損失として貸倒引当金繰入額が計上されます。
販管費と営業外費用に計上された貸倒引当金繰入額は、債務の確定がないので、法人税法22条3項2号の「費用」に該当せず、損金算入は一旦否定されますが、法人税法52条の貸倒引当金に関する別段の定めにより、限度額の範囲内で損金算入が認められます(法人税法22条3項2号(債務の確定と引当金)参照)。
他方、特別損失に計上された貸倒引当金繰入額は、同じく債務の確定がないので、法人税法22条3項3号の「損失」に該当せず、損金算入は一旦否定されますが、法人税法52条の貸倒引当金に関する別段の定めにより、限度額の範囲内で損金算入が認められます(法人税法22条3項3号(損失)の概要と法人税法33条との関係性参照)。
以上、貸倒損失と貸倒引当金の法人税法上の取扱いをまとめると以下のようになります。
・債権の全額が回収不能であることが確定していることで企業会計上「貸倒損失」を計上した場合・・・法人税法22条3項3号の「損失」として損金算入が認められる
・債権の全部または一部が回収不能と見込まれ、企業会計上「貸倒引当金繰入額」を販管費又は営業外費用に計上した場合・・・債務の確定がないので法人税法22条3項2号の「費用」にあたらず、損金算入は一旦否定されるが、法人税法52条の規定により限度額の範囲内で損金算入が認められる
・債権の全部または一部が回収不能と見込まれ、企業会計上「貸倒引当金繰入額」を特別損失に計上した場合・・・債務の確定がないので法人税法22条3項3号の「損失」にあたらず、損金算入は一旦否定されるが、法人税法52条の規定により限度額の範囲内で損金算入が認められる
貸倒が懸念される債権を売却することにより計上される貸倒損失の法人税法上の取扱い
貸倒が懸念される債権を保有していても、当該債権の全額の回収不能が確定しなければ、貸倒損失を計上できません。
そこでこのような貸倒れが懸念される債権を売却した場合はどのようになるのでしょうか。例をあげて説明します。
当社はE社に100万円の売掛金を有していました。当該債権の貸倒れが懸念されるため、当該債権をF社に40万円で譲渡しました。この場合の仕訳は以下のようになります。
現金 40万円/売掛金 100万円
貸倒損失 60万円/
このように、全額の回収不能が確定していない債権であっても、当該債権を売却すれば損失は確定するため、「災害等による資産損失」として法人税法22条3項3号の「損失」に該当し、損金算入が認めれます(法人税法22条3項3号(損失)の概要と法人税法33条との関係性参照)。。
全額の回収不能が確定していない債権については貸倒損失を計上できない理由
貸倒損失を計上できるのは、全額の回収不能が確定した債権に限定されます。
つまり全額の回収不能が確定していない債権は、企業会計上も租税法会計上も貸倒損失を計上することはできないと思われます。
✔企業会計上、全額の回収不能が確定していない債権につき貸倒損失を計上できない理由
企業会計基準第10号(金融商品に関する会計基準)において、以下のように記載されています。
Ⅳ 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等
1、債権
14.受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする
つまり企業会計上、債権につき貸倒れが見込まれる場合は、評価損(つまり貸倒損失)を計上するのではなく、貸倒引当金を設定し、債権額から貸倒引当金を控除することにより、債権金額を求めることを要求しているのです。
したがって企業会計上は
全額の回収不能が確定した債権・・・貸倒損失を計上
全額の回収不能が確定しない債権・・・貸倒引当金繰入額を計上
という棲み分けができているという事です。
✔租税法会計上、全額の回収不能が確定していない債権につき評価損(貸倒損失)を計上できない理由
法人税法における所得計算は、企業会計上の収益・費用を出発点とし、これを租税法会計に持ち込み、別段の定めにによる調整を加えて計算します。
企業会計においては、全額の回収不能が確定していない金銭債権については、評価損(貸倒損失)を計上するのではなく、貸倒引当金を設定する方法が採られています。したがって、租税法会計においても、この会計処理を基礎とする以上、全額の回収不能が確定していない債権の評価損(貸倒損失)を法人税法上損金として計上することはできず、貸倒引当金を損金としてすることになります。
この点、法人税法は33条1項で資産の評価損の損金算入を原則として否定しつつ、同条2項において災害等による著しい損傷の場合に限り例外的に損金算入を認めています。しかし、同条2項にいう「資産」には通常、金銭債権は含まれないと解されています。なぜなら、全額の回収不能が確定していない金銭債権については、貸倒引当金繰入額を損金算入するという制度(法人税法52条)が定められており、33条2項の「資産」に当該金銭債権を含ませて、評価損(貸倒損失)を損金算入させる必要がないからです。
つまり、全額の回収不能が確定していない金銭債権の回収不能見込額の損金算入について、33条のドアは閉まっているが、52条のドアは開けられているということです。
このように法人税法は
・全額の回収不能が確定した金銭債権については、22条3項3号の「損失」として損金算入する
・全額の回収不能が確定していない金銭債権については、貸倒れが見込まれる場合に評価損(貸倒損失)ではなく、貸倒引当金繰入額を設定し、52条により損金算入する
という条文構造をしており、全額の回収不能が確定していない金銭債権について、企業会計上評価損(貸倒損失)を計上して、当該評価損を法人税法33条2項で損金算入するという条文構造をとっていないのです。
このことは、法人税基本通達や法人税法施行令の文言からも読み取ることができます。
法人税基本通達9-1-3の2は「法人の有する金銭債権は、法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の評価換えの対象とならない」と明記しています。また、法人税法33条2項は資産の評価損を損金算入ができる場合について、施行令68条に委任していますが、施行令68条1項に列挙された資産の中に金銭債権は含まれていません。このような所からも、全額の回収不能が確定していない金銭債権の評価損(貸倒損失)の損金算入は予定されていないことが読み取れます。
法人税法52条による金銭債権の貸倒引当金繰入額の損金算入の縮小
全額の回収不能が確定していない金銭債権につき貸倒れが見込まれる場合、当該債権に対して企業会計上設定された貸倒引当金繰入額は、法人税法52条の規定により限度額の範囲内で損金算入が認められます。
しかし、52条の貸倒引当金の損金算入制度は平成23年度に改正され、貸倒引当金の損金算入が認められる法人が資本金1億円以下の中小法人や銀行、保険会社などに限定されることになりました(法人税法22条3項2号(債務の確定と引当金)参照)。
つまり当該改正により、資本金が1億円超の法人は52条を適用できず、貸倒引当金繰入額を損金算入できないことになったのです(52条による貸倒引当金繰入額の損金算入のドアが閉ざされたことになります)。
この改正は以下のような大きな問題を孕んでいます。
例えば、資本金1億円超のA社とB社が存在するとします。
A社は1,000万円の金銭債権を有していましたが、その全額の回収不能が確定したため、企業会計上これを貸倒損失として計上し、法人税法22条3項3号の「損失」として損金算入しました。
他方、B社も同様に1,000万円の金銭債権を有していましたが、全額回収不能となる可能性が高いものの、未だ回収不能が確定していないため、企業会計上貸倒損失として計上し損金算入することはできません。企業会計上は、例えば回収不能見込額80%として800万円の貸倒引当金繰入額を計上することはできますが、法人税法52条により、資本金1億円超の法人については当該貸倒引当金繰入額の損金算入は認められません。
この結果、A社とB社はともに回収不能と言える同じような債権を有しているにも関わらず、回収不能が「確定」しているか否かという一点の差により、A社は1000万円の貸倒損失の損金算入が認められる一方、B社は1円も損金算入することができず、A社とB社の間で大きな課税上の不公平が生じることになります。
興銀事件
興銀事件(最判平成16年12月24日民集58巻9号2637頁)は「金銭債権につき全額の回収不能が確定したと言えるか否か」が争点となった事件でした。
今回のテーマである「金銭債権の貸倒損失」に関連する判例であるため、興銀事件を取り上げて説明したいと思います。
✔興銀事件の概要
興銀事件とは、当時の日本興業銀行が住宅金融専門会社(住専)に対して有していた約3,760億円の貸付債権について、その全額が回収不能であるとして貸倒損失を計上し、これを損金算入して法人税申告を行ったところ、課税庁が当該債権の全額回収不能は客観的に確定していないとして損金算入を否認したため、その適否が争われた事件です。
判決の結果、興銀側が勝訴し、約3760億円の貸付債権についてその全額の損金算入が認められることになりました。
✔判決の内容
この事件では「約3760億円の貸付債権につき、その全額の回収不能が確定したと言えるか否か」が争われました。
債権の全額の回収不能が確定したと言えるなら、企業会計上「貸倒損失」を計上することができ、当該「貸倒損失」は法人税法22条3項3号の「損失」として損金算入できることになります。
他方、債権の全額の回収不能が確定したと言えなければ、企業会計上「貸倒損失」を計上することはできず、回収不能額を見積もって「貸倒引当金繰入額」を計上し、法人税法52条の貸倒引当金の規定の適用を受けて、限度額の範囲内でしか損金算入が認められないことになります(事件当時、「資本金が1億円超の法人は、法人税法52条の貸倒引当金の損金算入の規定を受けることができない」という文言は存在しなかったため、資本金が1億円超である興銀も52条の適用を受けることができます)。
判決では「債権の全額の回収不能が確定した」と判断するための基準が示されました。それが以下の基準です。
「債権の全額の回収不能が確定した」と判断するための基準
① 全額回収不能であること(部分貸倒れの状態では損金算入は一切認められない)
② ①の全額回収不能であることが客観的に明らかであること
の2つを要求し、これらを満たせば「全額回収不能である」としました。そして、①と②を判断するために、
③ー1 債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情
③ー2 債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情
③ー3 経済的環境等
を考慮事項とし、具体的な判断方法として、
④ 社会通念に従って総合的に判断する
という基準が示されました。
注目すべきは「③ー2 債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情」を考慮事項としたことです。
通常、貸倒れというと債務者側の事情(資産状況や支払い状況)に目が行くところですが、最高裁は両者の事情に目を向けたところに特徴があります。
もっとも、興銀事件以外の一般的な判断においては、まず重視されるべきは債務者側の事情(資産状況や支払い状況)だと思われます。
費用収益対応の原則という視点で見た貸倒引当金と貸倒損失
貸倒引当金は売上があった期における金銭債権に対して設定されるものなので、売上とそれに対応する貸倒引当金繰入額が同じ事業年度に計上されて収益と費用が対応します。
これに対して貸倒損失は、金銭債権の全額の回収不能が確定したときに計上するため、売上による収益計上時期と、当該売上に係る金銭債権の貸倒れによる損失の計上時期がづれて、収益と費用が同一の事業年度で対応しないことになります。