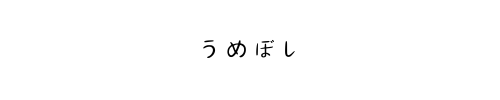人が生活していくためには、基本的には労働によって収入を得る必要があります。
そして、個人事業であっても法人であっても、さまざまな立場の人が関わり、働くことで収入を得ています。
個人事業では、事業に関わる人として「①個人事業主本人、②従業員、③親族従業員、④業務委託を受ける者」などがいます。
一方、法人でも「①役員、②従業員、③親族従業員、④業務委託を受ける者」などが事業に関わります。
このうち「②従業員と④業務委託を受ける者」については、個人事業か法人かによる大きな違いはなく、支払う報酬はいずれも必要経費として扱われます。
これに対し「①個人事業主本人と法人の役員、また③親族従業員」については、個人事業と法人とでお金の受け取り方や税務上の扱いが異なります。特に、個人事業主が法人を設立すると役員となるため、事業で得た利益の受け取り方が大きく変わります。
この記事では、①について「個人事業における事業主の所得と、法人における役員給与の違い」と③について「個人事業における親族従業員の給料と、法人における親族従業員の給料の違い」を中心に解説します。
個人事業における事業主の所得と、法人における役員給与の違い
✔経営者が事業利益を受け取る方法の違い
経営者が事業で得た利益の受け取り方は、個人事業主の場合と法人(役員)の場合とで大きく異なります。
個人事業主の場合、事業収入から必要経費等を差し引いて所得を計算し、そこから税金等を支払った残りが、そのまま生活費となる「手取り」です。
これに対して、個人事業主が法人成りをすると、通常は法人の役員となり、事業で得た利益は役員報酬という給与の形で受け取ることになります(加えて、株主として配当を受け取る場合もあります)。
このように、同じ「事業で稼いだ利益」であっても、個人事業と法人ではその受け取り方が大きく異なります。
✔役員報酬と法人税法34条
経営者は、できるだけ納税額を抑えたいと考えるのが通常です。なぜなら納税とはある意味「自分が稼いだお金を国に奪われること」と言えるからです。
個人事業主の場合、節税の中心は必要経費や所得控除を適切に計上することになりますが、事業に関係しない支出は経費にできません。
一方、法人形態では、これに加えて役員報酬という仕組みが生じます。この仕組みは個人事業では存在しません。
役員報酬は、法人側では損金となり(損金算入制限あり)、役員個人では給与所得となるため、使い方によっては納税額を大きく左右します。
もし役員報酬に何の制限もなければ、役員報酬を操作することで、経営者の納税額を不当に減らすことが可能になってしまいます。そこで、このような租税回避を防ぐために、法人税法34条(役員給与の損金不算入規定)が設けられているのです。
法人税法34条(役員給与の損金不算入規定)について
個人事業には「役員」という立場や「役員報酬」というものがないため、所得税法には法人税法34条(役員給与の損金不算入規定)に相当する規定はありません。
ところで役員は法人の意思決定を担います。法人は物理的に存在せず、法人自身は意思決定できないのでこれを役員が担う訳です。そして「役員報酬の額」についても役員が法人の代わりに決定します。つまり「役員自身が自らの報酬額を決定できる」ということです。
たとえば法人所得として1億円がありました。このまま何もしなければ、この法人所得に法人税が課税されます。そのような場合に「役員報酬1億円を計上する」という意志決定を役員自身が行ったとします。この場合、法人税法34条がなければ、役員報酬1億円は損金となり課税所得はゼロとなって法人税は発生しません。
その一方で、役員個人には1億円の給与所得が生じます。そこで、損益通算が可能な資産の譲渡損などを計上すれば、給与所得と相殺して所得税をゼロにすることも理論上は可能です。こうしたことが現実にできてしまうと、法人税も所得税も支払わずに1億円を法人から個人に移転できてしまいます。
このような事態を防ぐために、法人税法34条で「役員給与の損金不算入規定」を設けています。
この法人税法34条の規定は「役員給与が毎月定額であったり(定期同額給与)、事前に税務署に通告している役員賞与(事前確定届出給与)などについては損金算入を認めるが、これらに当てはまらない役員給与の支払いは、損金算入を認めない」というものです。
従って先ほどの例で1億円の課税所得が残っているからと言って、これを役員給与として支給しても、定期同額給与や事前確定届出給与に該当しないため、当該1億円の損金算入は認められません(ただし、役員に1億円の給与を支払うことを制限している訳ではなく、支払いは自由だけど、その1億円の損金算入は認めない、としているのが法人税法34条の規定)。
個人事業主の親族従業員を利用した所得分散と法人における親族従業員に対する給与の支払いによる所得分散の違い
✔個人事業主の親族従業員を利用した所得分散
所得税は(超過)累進税率が適用されます。よって個人の所得が多ければ、それだけ高い税率が適用されて多くの所得税を納税しなければなりません。
この所得税の納税額を減らすための方法の一つが「所得分散」です。つまり「一つの大きな所得を1人に帰属させる」のではなく「一つの大きな所得を2人以上に帰属させる」なら所得が分散し、低い所得税率が適用されて、所得税の納税額を減少させることができるのです。
個人事業主が「所得分散」をさせるために使う手法のひとつが「親族を従業員にして、その親族従業員に給与を支払う」というものです。
たとえば、ある個人事業主の所得(収入金額ー必要経費ー所得控除)が2000万円でした。このままでは高い所得税率が適用されて多額の所得税を納税しなければなりません。そこで妻に従業員になってもらい、給料500万円を支払うことになりました。この場合、もし妻に支払った給料を必要経費に算入できるとすると、夫の所得は「2000万円ー500万円=1500万円」に減額し、妻に500万円の所得が移転することになります。つまり親族従業員に対する給料の支払いにより、2000万円の所得を夫1500万円、妻500万円に所得分散できるのです。
このように個人事業主は親族従業員を利用することにより、所得分散を行って所得税の納税額を減額させることができるため、このような所得分散は所得税法56条において原則制限されています(つまり、妻への給料の支払いはなかったものとみなされ、所得分割はできない)。しかし例外的に「青色申告をしている場合で、親族が専らその事業に従事し、労務の対価が相当と認められれば」所得税法56条の適用はなく、当該給料を必要経費に算入することが認められます(所得税法57条・青色事業専従者給与)。
✔法人における親族従業員に対する給与の支払いによる所得分散
法人税は比例税率が適用されるため、法人所得を分散しても法人税を減税させることは基本できません。
しかし法人でも、個人事業主が親族を従業員として雇うのと同じように、法人の役員の親族がその法人の従業員となることがあります。この場合、一種の所得分散が可能になります。
たとえば法人の適用税率が23,2%であり、法人の親族従業員の受ける給料の所得税率が10%であったとします。そうすると、法人の親族従業員に給与の支払いをすれば、その給与が法人の損金となり、法人所得がその分減少し、親族従業員の給与が増加します。つまり親族従業員の給与につき、法人税率23,2%の適用を逃れ、所得税率10%の適用を受けることができ、トータルの納税額は抑えられることになります。
このように「高い税率の下から低い税率の下に所得を移す」という意味で一種の所得分散と言えます。この所得分散を制限する規定が法人税法36条(過大な使用人給与の損金不算入)です。ただ、法人の役員の親族に対する給料の支払いというだけで損金不算入とすることは適当ではありません。なぜならそのような親族従業員も通常の従業員と同じように働いているからです。法人税法36条は親族従業員に対する給与の支払いが通常支払われる給与の額を超えている場合にその超えている部分の金額を損金不算入とする規定です。
✔個人事業主の親族従業員を利用した所得分散と法人における親族従業員に対する給与の支払いによる所得分散の違い
個人事業主が所得税法57条に基づき親族従業員に給料を支払った場合、その給与の支払額は必要経費となり、かつ親族従業員の給与となります。つまり、この場合は適正な給与の額の範囲内で完全な所得分散ができていると言えます。
一方で、法人役員の親族が従業員として働き、その給与が適正額の範囲内であれば損金算入が認められ、この範囲内で法人税率(例:23.2%)から所得税率(例:10%)への課税の付け替え、いわゆる一種の所得分散が可能になります。ただし、給与の適正額を超える部分については損金算入が制限されます(法人税法36条)。
このように両者を比較すると、所得税法57条と法人税法36条の共通点と相違点が見えてきます。
所得税法57条と法人税法36条の共通点
両者ともに親族に支払う給与について、無制限な所得分散を認めていないことです。つまり適正な給与の範囲内でのみ所得分散を認めている点で共通します。
所得税法57条と法人税法36条の相違点
所得税法57条の話は「一つの所得を2つ以上に分散し、低い所得税率の適用を受けることで所得税額を減額することができる」というものです。これに対して法人税法36条の話は「法人所得を給与所得に移し替え、当該所得につき法人税率(例:23,2%)から所得税率(例:10%)の適用を受けることで納税額を減額できる」というものです。